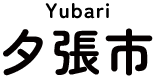本文
日本遺産「炭鉄港」
日本遺産とは
「日本遺産(Japan Heritage)」とは、日本の地域の歴史的魅力や特色を通じて、文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産(Japan Heritage)」として文化庁が認定するものです。
ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化財群を、地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、地域の活性化を図ることを目的としています。
【本邦国策を北海道に観よ!―北の産業革命「炭鉄港」ー】は令和元年度日本遺産に認定されました。
日本遺産ポータルサイト<外部リンク>
炭鉄港とは
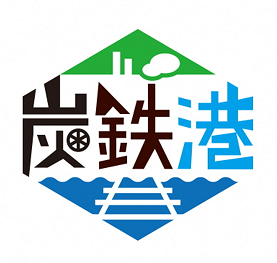 明治の初めに命名された広大無辺の大地「北海道」。
明治の初めに命名された広大無辺の大地「北海道」。
その美しくも厳しい自然の中で、「石炭」・「鉄鋼」・「港湾」とそれらを繋ぐ「鉄道」を舞台に繰り広げられた北の産業革命「炭鉄港」は、北海道の発展に大きく貢献してきました。当時の繁栄の足跡は、空知の炭鉱遺産、室蘭の工場景観、小樽の港湾そして各地の鉄道施設など、見る者を圧倒する本物の産業景観として今でも数多く残っています。100km圏内に位置するこの3地域を原動力として、北海道の人口は約100年で100倍になりました。その急成長と衰退、そして新たなチャレンジを描くダイナミックな物語は、これまでにない北海道の新しい魅力として、訪れる人に深い感慨と新たな価値観をもたらします。
炭鉄港 北の産業革命の物語<外部リンク>
夕張の炭鉄港ストーリー
 1874(明治7)年、アメリカ人鉱山地質学者ベンジャミン・スミス・ライマンの探検隊が夕張川上流の炭鉱地質を調査、その後1888(明治21)年、道庁の技師坂市太郎が志幌加別川の上流で石炭の大露頭を発見したことから「炭鉱の街夕張」の歴史が始まりました。1890(明治23)年に北海道炭礦鉄道会社(北炭)が夕張炭鉱を開鉱して以来夕張は炭鉱の街として栄え、北炭、三菱を中心に関連産業も発達していきました。
1874(明治7)年、アメリカ人鉱山地質学者ベンジャミン・スミス・ライマンの探検隊が夕張川上流の炭鉱地質を調査、その後1888(明治21)年、道庁の技師坂市太郎が志幌加別川の上流で石炭の大露頭を発見したことから「炭鉱の街夕張」の歴史が始まりました。1890(明治23)年に北海道炭礦鉄道会社(北炭)が夕張炭鉱を開鉱して以来夕張は炭鉱の街として栄え、北炭、三菱を中心に関連産業も発達していきました。
1960(昭和35)年には116,908人の人口を抱える都市となりましたが、昭和40年代になるとエネルギーの需要が石炭から石油へ移行したことにより次々に炭鉱は閉山していきました。1990(平成2)年に三菱石炭鉱業南大夕張炭鉱が閉山し「炭鉱の街夕張」としての歴史に幕を閉じ、その後夕張は「炭鉱から観光へ」と舵を切りました。
かつての炭鉱跡地を利用したテーマパーク「石炭の歴史村」が建設され、1980(昭和55)年には石炭博物館がオープンするなど、遺された炭鉱遺産は様々な形で活用されてきました。2007(平成19)年に夕張市は財政再建団体となりますが、石炭博物館が2018(平成30)年に全面改修を終え、マチや人々の営み、石炭産業について学ぶことができる中核施設としてリニューアルオープンするなど、炭鉱遺産は交流人口の創出や郷土愛を育む地域資源として利用され続けています。
構成文化財
1888年に、道庁技師・坂市太郎によって発見された。厚さ約7.3m(24尺)と大規模で貴重なものであるとともに、夕張の歴史の起点でもあります。
旧北炭夕張炭鉱天龍坑
1900年に開坑。入気・排気の坑口が対になって残っていること、赤レンガの化粧坑口が意匠的に美しいことが特徴です。

旧北炭鹿ノ谷倶楽部(夕張鹿鳴館)
1913年開設。北炭の賓客や会社幹部の宿泊・会合に用いられた福利施設で、1954年に昭和天皇が宿泊した際に、寝室・炊事場を大改造しました。
1925年に運転開始。北炭が所有する炭鉱の動力源として建設され、発電された電気は100km離れた歌志内まで送られました。
天龍坑の補助坑道を一部利用して1939年に見学用坑道として整備。地下で実物の炭層や採炭機械を見学できる国内でも珍しい施設です。(現在公開休止中)

旧北炭清水沢水力発電所
滝ノ上水力発電所と同様、炭鉱の動力源として建設され1940年に運転開始しました。

採炭救国坑夫の像
1944年に制作されたコンクリート製の塑像(高さ3.63m)。炭都・夕張のシンボルとして市民に親しまれ、戦時美術品としても価値があります。