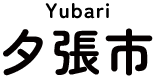本文
熱中症を予防しましょう
熱中症とは
『熱中症』は高温多湿な環境で発汗による体温調節等がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。
熱中症は屋外での仕事中や運動中に多くみられますが、屋内で何もしていない時でも発症し、救急搬送や場合によっては死亡することもあります。
気温が高くなくても、湿度が高いと体に熱がこもりやすくなります。
今後もこれまでにない暑さが続くことを想定し、一人一人が熱中症に関心を持ち、予防対策を積極的に行いましょう。
熱中症の症状
熱中症の重症度は「具体的な治療の必要性」の観点から以下のように分類されています。
| 症 状 | 対応と治療 | |
|---|---|---|
| 1度 (軽症) |
めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り) 意識障害を認めない |
応急処置と見守り 通常は現場で対応可能 冷所での安静、体表冷却、経口的に水分と塩分補給 |
| 2度 (中等症) |
頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下 |
医療機関へ 体温管理、安静、十分な水分と塩分の補給 |
| 3度 (重症) |
意識障害、けいれん、手足の運動障害、肝・腎機能障害、血液凝固異常 | 入院加療(場合により集中加療)が必要 |
熱中症が疑われたら、まずは応急処置をしましょう
・涼しい場所へ避難
風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内に避難させましょう。
・衣服を緩め、身体を冷やす
首の周り、脇の下、足の付け根等太い静脈部位に保冷剤や冷えたペットボトルなどを
タオルでくるんで当てましょう。
濡れたタオルを身体にあて、扇風機やうちわ等で風を当て水を蒸発させてからだを冷
やす方法もあります。
・水分・塩分を補給
冷たい水を自分で飲んでもらいます。冷たい飲み物は胃の表面からからだの熱を奪い
ます。
大量の発汗があった場合は、汗で失われた塩分も適切に補える経口補水液やスポー
ツドリンク等が最適です。食塩水(水1リットルに1~2gの食塩)も有効です。
応急処置をしても症状が改善されない場合は医療機関を受診しましょう。
自力で水が飲めない、意識がない場合はためらわず救急車を呼びましょう!
熱中症になる前の予防対策
≪暑さを避ける≫
・暑い日は無理をせず、扇風機やエアコンで温度を調節しましょう。
・遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用しましょう。
・室温をこまめに確認しましょう。
・外出時には涼しい服装で、日傘や帽子を着用しこまめに休憩することが大切です。
・体調が悪いと感じたら、無理せず休み、特に熱中症警戒アラートが出ているときは、
外出を控えましょう。
≪からだの蓄熱を避ける≫
・通気性のよい吸湿性・速乾性のある衣服を着用しましょう。
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす
≪こまめに水分補給をする≫
・のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。
・通常の水分補給には水・お茶を。スポーツ飲料などには糖分を多く含むものもある
ので飲みすぎには注意が必要です。
・1日あたり1.2リットルが目安です。5~15℃で吸収がよく、冷却効果も大きくなります。
・起床時、入浴前後に水分補給をしましょう。
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに。
・アルコール飲料での水分補給はダメです。摂取以上の量が尿で失われてしまいます。
≪高齢者と幼児は特に注意が必要です≫
高齢者は温湿度に対する感覚が弱くなるため室内でも熱中症になることがあります。
また、幼児も体温の調節機能が十分ではないため注意が必要です。
室内に温湿度計を置き、こまめな水分補給を心がけましょう。
熱中症予防のために 厚生労働省リーフレット [PDFファイル/882KB]
高齢者のための熱中症対策 厚生労働省リーフレット [PDFファイル/704KB]
参考
【厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト】
【環境省 熱中症環境保健マニュアル】
熱中症環境保健マニュアル2022 [PDFファイル/9.61MB]